バルト海に臨むエストニアの首都タリン(Tallinn)は、中世の雰囲気を色濃く残した城塞都市だ。
13世紀にデンマーク人によって築かれ、その後ハンザ都市としてロシアとの貿易によって繁栄した。
また冷戦期には旧ソ連にとっての西側(特にフィンランド)への窓口であった。
そんな西欧と東欧の交差点、タリンを2025年9月上旬に観光した。
2泊3日の滞在だが、途中でナルヴァへ日帰りしたので、途切れ途切れで実質1日程度の時間だった。
1日目:下町
城壁で囲まれたタリンの旧市街は大きく2つに分かれている。
1つは旧市庁舎を中心に広がる下町。
もう1つが丘の上にあるトームペア。
下町から観光を始めるのが一般的だ。
タルトゥからの列車でタリン駅に着いたのが16時10分。
駅舎にあるスーパーマーケットの惣菜コーナーで今夜の夕食を調達する。


ところで、ここに限らずエストニアのスーパーの店員の接客レベルが非常に高いのは特筆される。
私のような外国人にも英語で積極的に助けてくれるし愛想も良い。
「エストニア=旧ソ連」というイメージを持っている人がいたら、今すぐそんな古臭い先入観は捨てるべきだ。
まずは旧市街北東端のふとっちょマルガレータ近くにある、聖オレフ教会を訪れる。


教会の内部は普通だったが、ここに来る目的は何と言っても塔からの眺めである。
今晩はオペラを観劇するのでジャケットを着用していたが、かなりの階段を登って暑かった。
しかし眺望はそんな不快さを吹き飛ばしてくれる。
城砦に囲まれたタリンの旧市街が、まるで模型のように眼下に広がっているのだ。
一段高い所にあるトームペアには大聖堂やロシア正教の教会が建っている。
北に目をやればタリン港が目の前にある。
大型のクルーズ船や、対岸のフィンランドのヘルシンキとを結ぶフェリーの姿があった。
ワルシャワに始まり、ついにバルトの最北まで辿り着いたのだ。


なおヘルシンキまでは約80㎞で、フェリーで僅か2時間である。
冷戦期にもかかわらず、1965年にタリン・ヘルシンキ間のフェリー便が開設され、ソ連にとっては唯一外の世界への輸送手段だった。
さらにエストニアではフィンランドのテレビ放送にもアクセスできたという。
ソ連時代のタリンは、西側世界との境界だったのだ。
良くも悪くも、タリンはバルト三国のなかで最も観光地化された都市である。
迷路のように入り組んだ街には土産物屋や観光客向けレストランがあちこちにあり、旧市街全体が中世の世界を体現している。


しかしそんなタリンの街で、唯一現実に引き戻されたのがロシア大使館だった。
建物の前にはウクライナ戦争に抗議するメッセージが溢れかえっていて、近くには警察も見張っていた。
“FOR THE VICTIMS OF WARS STARTED BY RUSSIA “と書かれた横断幕をよく見ると、BYの横に薄っすらとU.S.の文字とユダヤ人の「ダビデの星」らしきマークが描かれていた。
ウクライナ戦争とパレスチナ戦争に対する西側諸国のダブルスタンダードを見事に衝いた痛快なアートに拍手喝采を送りたい。

ちなみにエストニア前首相のカラス氏は今年、「ロシアのDNAには領土的野心が刻まれている」と発言した。
私はこれは政府批判を越えた悪質なヘイトスピーチであると思っている。
それでも彼女がその見解を固持するなら、せめて「ユダヤ人のDNAにも領土的野心が刻まれている」、あるいは「力による現状変更は認められないが欧米とイスラエルだけは除く」と同時に主張するのが筋というものであろう。
さて、中世のおとぎ話の世界に戻ろう。
旧市街には教会がたくさんある。
ロシア大使館の近くの聖霊教会は内部が暗く古風な雰囲気で、木彫りの装飾や祭壇が印象的である。
華やかさはないが、庶民に親しまれている教会のようだ。
ここがタリンで最も落ち着いた空間だった。
公園のような広場にある比較的大きな教会が聖ニコラス教会。
こちらは現在、中世美術の博物館になっている。
見どころは15世紀に描かれた宗教画で、特に王や貴族たちが黒い骸骨と一緒に踊っている「死のダンス」は有名だ。
14世紀に大流行したペスト(黒死病)によって、ヨーロッパ全体で人口の4分の1から3分の1が亡くなったとされている。
そんな惨状のなかで、死の普遍性を題材とする芸術や文学が普及したが、現存するものは少ないという。

ルネサンス前の絵画なのであまり写実的ではなく、全体的なタッチはのっぺりとしている。
だが、それでこそ余計に不気味に感じられるのである。
卑近な喩えで恐縮だが、昔のRPGのモンスターを考えてみよう。
オリジナル作品では荒いドット絵で描写されていたものが、リメイク版では活き活きと動く。
だが、「怖さ」という観点ではリメイク版のリアルなモンスターはオリジナル作品の静止画には敵わないのだ。
30代半ば以上の人なら分かってくれるだろうか?
ぶらぶらと歩きまわっていると、旧市街の中心となるラエコヤ広場に着いた。
真ん中に旧市庁舎を抱き、周りにはレストランが軒を連ねている。
これまで滅多に目にしなかった日本人の姿も散見された。

1日目夜:オペラ観劇と幻想的な旧市街
夜19時からエストニア国立歌劇場でオペラを観劇する。
1913年に造られた建物は、「クラシックな劇場」のなかでは新しい方の部類に入る。
そのためかクリーム色を基調にした外観と内装は、優雅な曲線美を取り入れながらも全体的にすっきりとした印象だ。

今夜の演目はドニゼッティの「ドン・パスクワーレ」。
あらすじは独身の老人を結婚詐欺まがいの策略ではめるというもので、はっきり言って非倫理的な話である。
全体的に曲調・雰囲気は大変明るく美しいのだが、それは台本の罪滅ぼしなのか、作品をより一層残酷なものにしているのか、どちらだろうか?


クラシックファンにとって、ソ連時代の(数少ない)豊かな遺産を引き継ぐロシア・旧ソ連諸国は穴場である。
ヴィリニュス・リガそしてタリンと、バルト三国の各首都でオペラ鑑賞をしてきたわけだが、その水準の高さの割には観光客はほぼいなかった。
特にウィーン・プラハ・ベルリンの劇場やホールでは必ず日本人(もっとも最近は日本人が減って中国人・韓国人の方が増えている)がいるものだが、バルト三国では全くアジア人に会わなかった。


幕が閉じたのは21時半頃。
夜の旧市街があまりにロマンチックなので、すぐにホテルに帰るのは勿体なく思えてきた。
まだまだ観光客で賑わっているのだが、不思議なことに街の空気はしっとりとして静かだ。
首都でありながら古い田舎町らしさも併せ持つ、タリン旧市街のなせる業である。


ホテルに帰って、用意していた夕食と共にオペラの余韻に浸る。
「エストニア伝統料理」のような仰々しいものは必要ない。
茹でたジャガイモと白身魚フライとベーコン、そしてライ麦パンと缶ビールがあれば、これ以上ないご馳走である。
2・3日目:トームペア

2日目の午前中はトームペアに行く。
下町から趣のある階段を登りきると、目の前にはロシア正教会のアレクサンドル・ネフスキー聖堂が鎮座していた。
タリンの人口のうちロシア人は4割弱を占めるという。
スカーフをした信者が続々と訪れて、イコンに接吻したり十字を切る。
観光地化されたプロテスタント教会が多いのに対し、ここはロシア系少数民族の心の拠り所となっているようだ。

そのすぐ目の前には、代々の権力者が住んだトームペア城がある。
13世紀に建てられて以来増改築が繰り返されたため、現在は宮殿のような外見になっている。
ただ外壁と幾つかの塔だけが中世の姿をとどめている。
細長い塔ののっぽのヘルマンが高々とエストニア国旗を掲げていた。
今も政府機関として使われているので、内部を見学することはできない。

大聖堂(聖母マリア教会)はエストニア本土最古の教会だ。
内部に入ればすぐにその歴史的価値が分かる。
床には墓石が眠り、壁には多数の紋章が飾られており、教会よりも市庁舎のようだった。
掲げられている旗のなかにはデンマーク国旗もある。
13世紀前半にデンマーク人によって建設されたタリン市にとっては、デンマークの存在は大きなものなのだろう。
大学都市タルトゥ(エストニア第二の都市)が、大学設立に深く関わったスウェーデンに愛着を抱くのと同じかもしれない。


大聖堂の近くには幾つか展望台があり、旧市街やその向こうのフィンランド湾を見渡すことができる。
最後に訪れたのは、旧市街の南側の城砦を利用した博物館のキーク・イン・デ・キョクだ。
タリンを象徴する場所と言ってよい。
実際の旅程では3日目の朝である。

この施設は城壁と複数の塔と地下トンネルで構成されている。
塔の内部はタリン旧市街に関する博物館になっていて、歴史を説明する動画や騎士の剣術を体験できるコーナーまであった。
狭くて急な階段は沢山の観光客で渋滞していた。
城壁は石の壁に木の床と柵を取り付けたもので、中世の雰囲気に浸れる。
施設内にはカフェもあって、購入したものを城壁で飲むこともできた。


入り口に戻って地下トンネルへ。
17世紀のスウェーデン支配時代に造られた設備で、戦時中は防空壕として、冷戦中も核シェルターとして使われたという。
塔と城砦の中世ロマンとは対照的に、暗くて足元が悪い不気味な通路である。
結構リアルなマネキン人形もあるので、心臓が弱い人は覚悟しておいた方が良い。


トンネルの最後の方には石の彫刻が飾られていた。
どれもいきなり動き出しそうな雰囲気を湛えている。
トンネルの出口は城壁外部の自由広場なので、上着などを預けている人は注意しよう。
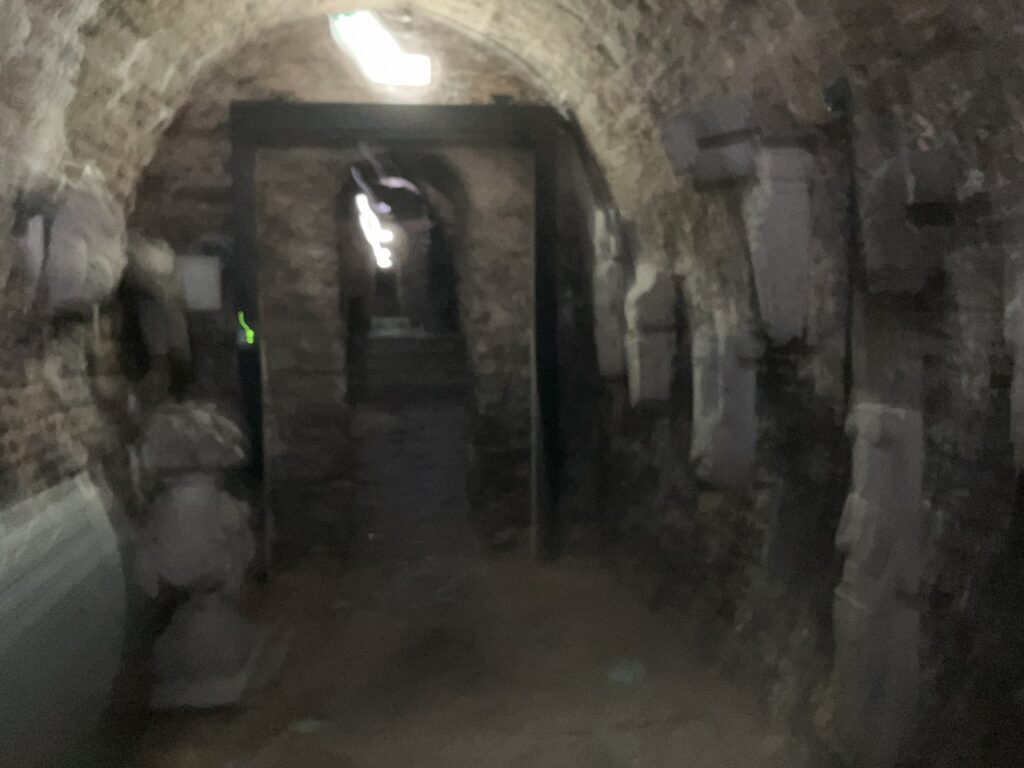
トンネルから出た時はホッとした。
11時の開場と同時に入って、今が13時前だから2時間弱滞在したことになる。
地下トンネルはやや駆け足になったから、見学時間の目安は2時間以上といったところだろう。
歴史的建造物の価値を保持しながらも色々と工夫された博物館なので、時間が限られている人も、タリン観光にキーク・イン・デ・キョクは外さないようにしよう。
これで10日間のバルト三国旅行の日程を全て終えた。
鉄道の高い定時性のおかげで、予想以上に順調にスケジュールをこなすことができた。
私の実質的なタリン滞在は丸1日程度だったが、最低限のものは一通り見ることができたと思っている。
もし2日間あればカフェやレストランでゆっくりしたり、他の興味がある博物館に行くこともできるだろう。
これから帰りの空港に行かなければならない。
預けているスーツケースを取りに駅まで歩いていると、冷たい雨が降り始めた。



コメント